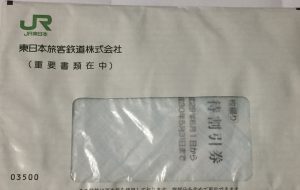ある時、職場の人にこんなことを言われました。「○○さん、九州まで行って吉○家に入ったって本当ですか!?」そこで自分は誤解を解くために言いました。「違います。吉○家には行ってませんよ。○屋です!」どっちも変わらないんでしょうかね。ですが、相手は驚いていました。自分はさらに続けました。「福岡の○屋と東京の○屋は違うんです!」理解してもらえなかったのは言うまでもありません。
さて、旅行に行ったらどこで食事を取るべきなのでしょうか?自分は移動中心の行動ですので、途中停車や乗り換え時に立ち食いそばを多用するのですが、さすがに夜はちゃんとしたものを食べたいので、ご当地の飲食店を利用します。ですが、基本的にチェーン店(しかも全国展開が多い)なので、それが一般の人に理解されないようなのです。どこでも食べられるものを、なぜ旅先で食べるんだ?
旅慣れた人は(全員ではないでしょうが)地元のお店ではなく、全国展開のチェーン店を利用することが多いと思います。ですが、あまり旅をしない人からすれば、せっかく地方に行ったのだから、地元の名産品を食べるべきなのではないか、そういう疑問をぶつけられます。ですので、ここでなぜ自分がチェーン店を利用するのか、と言うよりなぜ地元のお店に行かないのか、その理由を述べたいと思います。
- 提供スピードが遅い
都会のお店では、結構スピードが重視されます。のんびりしているとお客さんを捌けませんので。ですが、地方は比較的のんびりしています。オーダーを取ってから30分くらい待つのも珍しくありません。そのお店の食事を楽しみたいのならいくらでも待ちますが、我々は移動する行程の一部で食事を取りたいのです。そのため、食事のために1時間も時間を割くことはできません。 - 当たり外れが多い
全国展開のチェーン店では、どこの店でもほぼ同じメニューが同じ品質かつ同じスピードで提供されます。それは我々にとっての安心感につながるものです。初めて行く地域のよく分からない店で不味いものを食べるよりは、いつも食べているメニューの方が安心できます。ちゃんと事前に調査をすればそれなりにおいしいものにありつけるかもしれませんが、我々の旅の目的は食事ではないのでそこまで時間をかけて調査することができません。お値段も観光地料金のところが多いですし。お店でギャンブルするよりは確実な味を求めるのは致し方ないことかと思います。 - 営業時間が短い
旅行において、基本的に日中は移動し続けるプランが多いです。日が暮れるまでなるべく移動して、ホテルにチェックインするのは早くて20時頃というパターンが多いのです。ですが、地方の飲食店は基本的に18時に閉まります。さらに、18時前にも関わらずどうせ客が来ないだろうからと30分前に閉店作業を始める店も珍しくありません。当日の目的地に着いて、さあ食事をしようと思っても開いている店は、せいぜい○野家か○屋かす○家かマクド○ルドということもよくあります。地元の名産品を扱うような店は既に閉店しているので、選択肢が限られるのです。確かにホテルの食堂が21時まで営業している場合もあるのですが、お値段がちょっと。某ホテルのおにぎりとカレーはありがたいですけど。
こんなこともありました。ある地方都市で夕食を取ろうとしたことがあります。その地域は海産物が有名ですので、せっかくだからそういう料理を味わってみようということにしました。店に入ると、中にいるのは学生バイトの店員ばかり。お値段の割には層が薄いな、なんて思ったのですが。注文を決めて、呼出しボタンを押しましたが、故障しているのかなかなか店員が来ません。数回押しても誰も来ないので、仕方なく厨房に出向き注文を伝えました。その時、自分と同じく注文をしようとしていたお客さんが同様に厨房に向かっているのを見ました。それからようやく料理が出てきましたが、正直言ってお値段ほどのグレードではなく、これはバイトレベルでもできそうだなという代物でした。店構えと価格帯を考えれば、それなりの料理が出てきて然るべきだと思ったのですがね。次回からは地元名物のカレーにしようと思ったのも無理からぬことでしょう。
さらに、別の地域では、そこは有名な神社の門前町でしたが、食事できそうな店が1軒しかなく、仕方なくその喫茶店に入ることにしました。その店では店員さんが高齢の方で、かなり声を張らないと注文ができません。自分はあまり大声を出すのが得意ではないので、注文を伝えるのにかなり苦労しました。実は隣駅まで行けばそれなりに店があるということを後で知ったので、その駅付近で食事をすることは二度とないでしょう。
旅慣れていない人は、せっかく旅行するのだからその地域の名産品を食べなければならないという固定観念があり、ともすればそれを他人に押しつける傾向が見られることもあります。アドラー事件で疎遠になったあの方もそうでしたけど。ですが、自分も時間が合えば地元の名産品を食することもあります。ただ、旅行のメインが食事ではないため、食事する場所が立ち食いそばかチェーン店になりがちということなんです。
いわゆるフツーの旅行をする人は、朝出発して昼に目的地に到着、そこで昼食を取ることと思います。夜は、ホテルなり居酒屋なりで食事ができるので、地元の名産品を食する機会があるわけです。しかし、自分のように移動がメインですと、昼間はもっぱら移動に当てすき間の時間で食事をするためにそば類を取ることが多い、夜に目的地(宿泊地)に到着すると開いている店は24時間営業または20時まで開いているチェーン店またはコンビニしか選択肢がありません。チェックイン前に食事を取るかコンビニ弁当持ち込みの方が効率がいいので、居酒屋という選択肢はありません(特に一人ですので)。
旅の目的(テーマ)の違いもあるかもしれません。旅行というものは、とりあえず移動して旅先の景色を楽しむ、食事を楽しむ、温泉やテーマパークなどの施設で遊ぶというスタイルが一般的なんでしょうが、自分のようにひたすら移動し位置ゲーに熱中するスタイルでは、不確定な要素を排して確実なチェーン店、または店が閉まっているのでコンビニで弁当などを買うことが多くなります。前にも書きましたが、旅の目的は人それぞれなので、個人の趣向を他人に押しつけるのはよろしくないのではないかと思います。特に「旅先では必ず地元の名産品を食べなければならない」などと強制するのはもっての外だと思います。理解されないところは諦めているのですが、自分の考えを押しつけるのだけはご遠慮いただきたいと切にお願いする次第です。