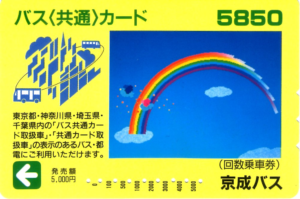JRの大都市近郊区間における大回り乗車について書いてきましたが、旅客営業規則に記載されている大都市近郊区間を見てみると世間で認識されている路線名と違う記載があることに気が付きませんか?
ここで旅客営業規則第156条を確認してみましょう。
第156条
旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
実は途中下車に関する規定の条文なのですが、ここに大都市近郊区間の記載があります。途中下車については今回は無関係なので省略します。いろいろ思い出というか遺恨はありますけど。
(2)次に掲げる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京附近にあっては、東海道本線中東京・熱海間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。)及び品川・新川崎・鶴見・羽沢横浜国大間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、伊東線、中央本線中東京・塩尻間及び岡谷・辰野・塩尻間、青梅線、五日市線、八高線、小海線中小淵沢・野辺山間、篠ノ井線中塩尻・松本間、東北本線中東京・黒磯間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)東京・那須塩原間を除く。)、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・浪江間、川越線、高崎線(第16条の2の規定にかかわらず、高崎線(新幹線)大宮・高崎間を除く。)、上越線中高崎・水上間、吾妻線、両毛線、水戸線、日光線、烏山線、水郡線中水戸・常陸大子間及び上菅谷・常陸太田間、信越本線中高崎・横川間、総武本線、京葉線、外房線、内房線、成田線、鹿島線、久留里線及び東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)
なんか見たことがない記載が多いぞ?品川・新川崎・鶴見・羽沢横浜国大間?赤羽線?という疑問が起こるのはごもっとも。今のJR東日本はそんな案内は出してません。案内看板にそんな書いてあるのを見たことがありませんよね。実は路線の正式名称なのです。品川・新川崎・鶴見というのは横須賀線(湘南新宿ライン)の一部、鶴見・羽沢横浜国大というのは埼京線・相鉄直通線の一部?、赤羽線は埼京線の一部(池袋~赤羽間)、日暮里・尾久・赤羽は上野東京ラインの一部、赤羽・武蔵浦和・大宮間は埼京線の一部なのです。なお、東海道新幹線(東京~熱海間)、東北新幹線(東京~那須塩原間)、上越新幹線(大宮~高崎間)は含まれないことも明記されています。
ロ 大阪附近にあっては、東海道本線中米原・神戸間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)新大阪・新神戸間を除く。)、山陽本線中神戸・相生間(第16条の2の規定にかかわらず、山陽本線(新幹線)新神戸・西明石間を除く。)及び兵庫・和田岬間、湖西線、おおさか東線、大阪環状線、桜島線、JR東西線、福知山線中尼崎・谷川間、北陸本線中米原・近江塩津間、加古川線、赤穂線中相生・播州赤穂間、山陰本線中京都・園部間、関西本線中柘植・JR難波間、草津線、奈良線、桜井線、片町線、和歌山線、阪和線及び関西空港線(以下これらの区間を「大阪近郊区間」という。)
説明が要りそうなところだけ書いておくと、桜島線=JRゆめ咲線、片町線=学研都市線、関西本線柘植・JR難波間(加茂~JR難波間は大和路線)ぐらいでしょうか。なお、山陽新幹線の新大阪~西明石間は含まれません。ということは、東海道新幹線の米原~新大阪間と山陽新幹線の西明石~相生間はなんと含まれるのです!最短きっぷで新幹線の改札に突っ込むと駅員とケンカになりそうですけど。
ハ 福岡附近にあっては、鹿児島本線中門司港・鳥栖間(鹿児島本線(新幹線)小倉・博多間を除く。)、香椎線、篠栗線、日豊本線中小倉・行橋間、日田彦山線中城野・今山間、筑豊本線、後藤寺線及び博多南線(以下これらの区間を「福岡近郊区間」という。)
山陽新幹線小倉~博多間はJR西日本の管轄ですので、当然含まれません。でも、西日本管轄の博多南線はOKなのか?よく分からないです。また、筑肥線は含まれません。まあ、福岡市内駅からもハブられてるぐらいですから、仕方ないですね。蛇足ですが、香椎線=海の中道線(西戸崎~香椎間)を含む、筑豊本線=若松線&福北ゆたか線(折尾~桂川間)&原田線、篠栗線=福北ゆたか線の一部(桂川~吉塚間)です。
ニ 新潟附近にあっては、上越線中小千谷・宮内間、磐越西線中五泉・新津間、羽越本線中新津・村上間、白新線、信越本線中直江津・新潟間(第16条の2の規定にかかわらず、信越本線(新幹線)長岡・新潟間を除く。)、越後線及び弥彦線(以下これらの区間を「新潟近郊区間」という。)
特に説明するところもなさそうですが、上越新幹線の長岡~新潟間が含まれない事だけは書いておきます。
ホ 仙台附近にあっては、東北本線中矢吹・平泉間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)郡山・一ノ関間を除く。)、岩切・利府間及び松島・高城町間、常磐線中小高・岩沼間、仙山線、仙石線、石巻線、磐越東線中船引・郡山間、磐越西線中郡山・喜多方間、奥羽本線中福島・新庄間(奥羽本線福島・新庄間に運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。)、左沢線及び陸羽東線(以下これらの区間を「仙台近郊区間」という。)
東北新幹線郡山~一ノ関間は含まれません。それと東北本線松島・高城町間?そんなところに線路あったっけ?路線図上には出てきませんが、実際には存在します。東北本線松島、仙石線高城町の手前(仙台方)に架線の途絶えた謎の連絡線があります。それが松島・高城町間というわけです。よーするに、仙石東北ラインのことですね!それと福島・新庄間(福島・新庄間に運転する特別急行列車に乗車する場合を除く)というややこしい表現はいったい何なんだ?結論を言えば、山形新幹線(つばさ号)は含まれないという意味です。面倒ですが、一応書いておくと第3条に用語の定義があり、そこで新幹線の定義もされているのです。
第3条 この規則におけるおもな用語の意義は、次のとおりとする。
(中略)
(1)の6 「新幹線」とは、東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)、鹿児島本線(新幹線)、東北本線(新幹線)、東北新幹線、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)、信越本線(新幹線)、北陸新幹線、九州新幹線及び北海道新幹線をいう。
えーと、何を書いているのか分からないという方のために説明すると、フル規格の新幹線以外は新幹線として認めねえ!と書いています。よって、山形新幹線、秋田新幹線といったいわゆるミニ新幹線は在来線扱いです。九州新幹線の武雄温泉~長崎間(建設中)はフル規格なので新幹線になることでしょう。それと蛇足ですが、ゆうゆうあぶくまライン=磐越東線、山形線=奥羽本線の一部(福島~新庄間)です。
また、乗車経路の扱いについてですが、列車の運行パターン(停車パターン)によって、一部区間外乗車が認められている箇所があります。おそらく大回り乗車でも準用されるのではないかと。
1.松島または愛宕以遠(品井沼方面)の各駅と高城町以遠(松島海岸または手樽方面)の各駅との相互間[塩釜~松島]
松島方面から仙石東北ラインに乗るために塩釜で折り返していいよという扱いです。その逆も可能です(以下同じ)。
2.西日暮里以遠の各駅と三河島以遠の各駅との相互間[日暮里~東京]
常磐快速線から上野東京ラインに乗るために東京まで行っていいよという扱いです。上野ではなく東京なのは、新幹線を想定しているのでしょう。
3.日暮里、鶯谷または西日暮里以遠及び三河島以遠の各駅と尾久駅との相互間[日暮里~上野、鶯谷~上野]
上野東京ライン尾久から山手線、京浜東北線(鶯谷方面)または常磐線(日暮里方面)まで行くのに上野で折り返していいよという扱いです。
4.西大井以遠(武蔵小杉方面)の各駅と品川以遠(高輪ゲートウェイ方面)の各駅との相互間[品川~大崎]
湘南新宿ラインから山手線(品川以遠)に行くのに、大崎折返しでもいいよという扱いです。てか、横須賀線乗れよ。
5.横浜以遠(保土ケ谷または桜木町方面)の各駅と羽沢横浜国大駅との各駅相互間[鶴見~武蔵小杉]
相鉄直通列車は配線の都合で武蔵小杉からしか乗れません。なので、東海道本線、横須賀線の保土ケ谷、戸塚方面、あと根岸線からの利用時に鶴見~武蔵小杉の折返しを認めてやろうということです。鶴見は上述の通り品鶴線の終点ですので、本来はそこで折り返さないといけないのですが、いかんせん電車が停まらないので。
6.新川崎駅と羽沢横浜国大駅間との各駅相互間[新川崎~武蔵小杉]
相鉄直通列車は配線の都合で新川崎に停まれません(真横にある新鶴見信号場を通過します)。なので、新川崎から武蔵小杉までの折返しを認めてやろうということです。この相鉄直通線は特殊なルートを通るのでやむを得ないところでしょう。
7.鶴見、新子安、東神奈川または川崎以遠(蒲田または尻手方面)、国道以遠(鶴見小野方面)もしくは大口以遠(菊名方面)の各駅と羽沢横浜国大駅との各駅相互間[鶴見~横浜、新子安~横浜、東神奈川~横浜、鶴見~武蔵小杉]
これも相鉄直通列車の特異性によるものです。京浜東北線、鶴見線、横浜線から横浜経由横須賀線または湘南新宿ラインで武蔵小杉まで行っていいよという扱いですね。
8.鶴見、新子安、東神奈川または川崎以遠(蒲田または尻手方面)、国道以遠(鶴見小野方面)もしくは大口以遠(菊名方面)の各駅と、新川崎、西大井または武蔵小杉以遠(武蔵中原または向河原方面)の各駅との相互間[鶴見~横浜、新子安~横浜、東神奈川~横浜]
品鶴線の終点は鶴見ですが、そんなところに横須賀線、湘南新宿ラインの電車は停まらないので、横浜で折り返していいよという扱いです。京浜東北線の鶴見~東神奈川間から横浜へ折り返して横須賀線(湘南新宿ライン)の品川・大崎方面に乗れます。
9.武蔵白石または浜川崎以遠(小田栄または昭和方面)の各駅と大川駅との相互間[武蔵白石~安善]
もともと鶴見線の大川支線は武蔵白石から発着していました。それが武蔵白石のホームが廃止され、大川行きは鶴見発着となりました。そのため、浜川崎方面から乗車する場合は、安善まで行ってから折り返すことが認められるようになりました。
10.今宮または芦原橋以遠(大正方面)の各駅とJR難波駅との相互間[今宮~新今宮]
大阪環状線の芦原橋以遠(大正方面)からJR難波に向かう場合に新今宮まで行って折り返していいよという扱いです。今宮駅は昔は大和路線にしかなく大阪環状線はその外側を通過していましたが、今は大阪環状線にも今宮駅ができました。ですが、今でも快速は今宮を通過するので必要なんですかね?
11.折尾以遠(水巻方面)の各駅と東水巻以遠の各駅との相互間[折尾~黒崎]
*ただし、鹿児島本線と筑豊線を直通する列車に乗車する場合に限ります。
地元民ならすぐ分かると思いますけど、鹿児島本線の門司港、小倉、黒崎発着の福北ゆたか線直通列車というのがあります。この列車は、配線の都合で折尾駅では他ののりばから離れた場所を経由します。なので、博多方面から黒崎まで戻ってその直通列車に乗っていいよという意味です。折尾~陣原でもいいのでは?いや、昔は陣原駅はなかったのでその名残でしょう。
繰り返しになりますが、巷のネット記事などでは大回り乗車についてあまりに簡単に書きすぎているように思います。実際にはここまで述べたような複雑なルールを理解した上でないと実行することはできません。青春18きっぷなら、間違えて特急に乗ったらその分の運賃を支払えばいいですが、大回り乗車についてはリスクが大きいように思います。しっかりルールを理解して楽しんでいただければと思います。